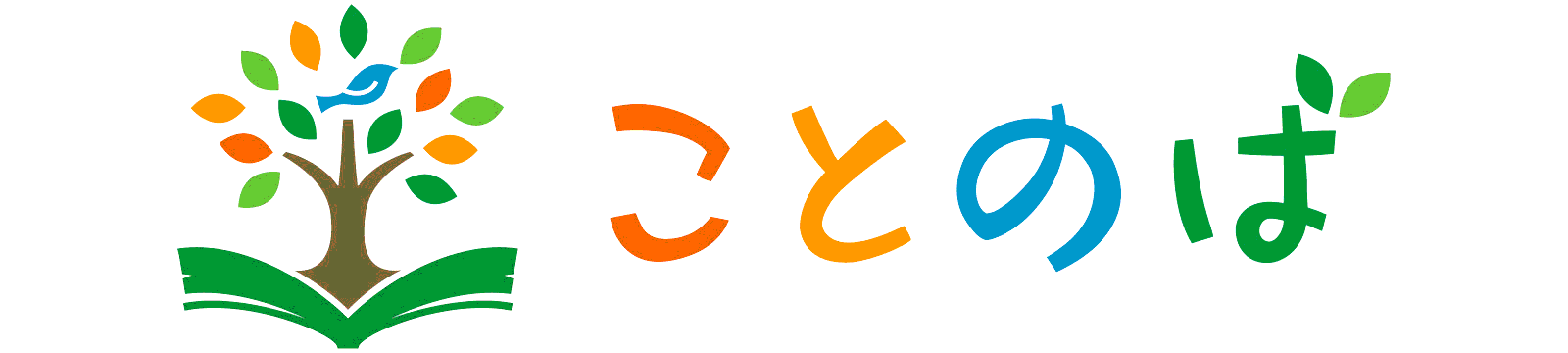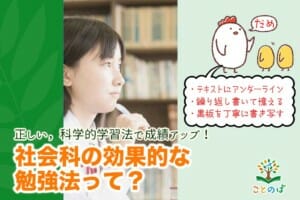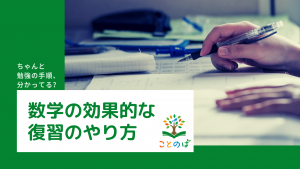中学生の2学期期末考査が終わり、続々と試験の結果が返ってきています。
前の記事で書いたのですが、今回、初めてお世話をしている子たちは、あまり厳しく追い込む指導をしていません。

だからこそ、なのですが、「試験後の復習」が非常に重要な意味を持っています。
ただし、ここでいう「復習」というのは、試験問題(間違った問題)のやり直しなんていう無意味な作業ではありません。
それについては、こちらの記事に書いたとおり。

ことのばでの「試験の振り返り」では、次のような3つのポイントを押さえておこないます。
1.試験の答案を生徒と一緒に分析する
大事なコトは「どのようなタイプの問題」を「どのように間違えた」か。
これは、当然といえば当然ですね。
2.試験勉強の取り組み表と照らし合わせる
「間違え」が生まれた原因となった「勉強のやり方」の粗を探ります。
- 繰り返した回数が足りなかったのか?
- 問題演習への取り組みが足りなかったのか?
- そもそも基礎が出来ていないのか?
そういったことを確認するためにも、「取り組みの型」、「プロセスのデザイン」を最初に指導していくわけです。
多くの場合は、ここで改善のポイントがはっきりします。
3.「自分なりにやれた」の客観性をチェックする
2のチェックで、「プロセスに特に問題がない」のに、1のチェックで「壊滅的にダメ」ということも起こります。
その原因は次の2つしかありません。
- A.基礎力(読解力、語彙力)が足りていない。
- B.「やった」のハードルが異様に低い。
A.基礎力(読解力、語彙力)が足りていない。
本来、中学校に入学した段階で、どれくらいの学力を身に付けているのか事前にチェックしておくのが理想ではあります。
(入学段階の全国学力テストの結果などから)
ただ、そこまでチェックしていないので(ざっくりし過ぎていてアテにならないという印象がありまして…)、試験の結果を
見て探っていくことになります。
B.「やった」のハードルが異様に低い。
試験勉強の途中に、「この範囲、やれたと思ったら報告に来て!」と指示し、勉強した内容を解説させると、その子がどのレベルで「勉強できた」と言っているかが分かります。
(個別の対応になるため、相当な手間がかかりますが。)
ただ、試験前にそこまで余裕がない場合も多く、試験の後、「次の試験への対策」を練っていく過程で同じことをする場合も多いものです。
いずれにせよ、生徒の「やりました」はアテにならない!が基本ですね。
といったところで、
 女子学生さん
女子学生さん試験勉強、がんばったのに思ったほど、成績が振るわなかった…
という場合の見直しポイントについてのお話でした。
参考にしていただければ幸いです。(^^)