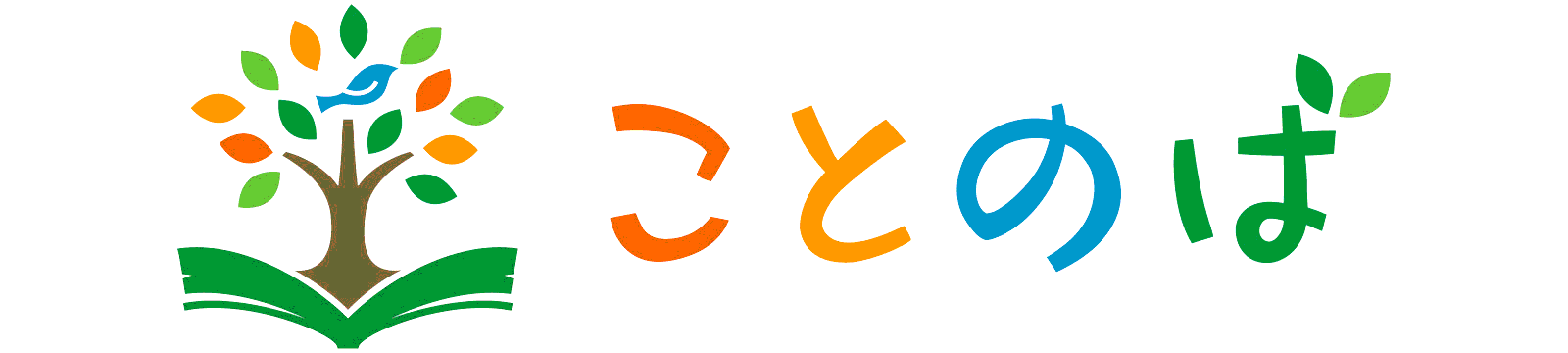日本学生支援機構(旧日本育英会)による長期滞納者への一括返還訴訟が増えているんだそうですよ。
返還が滞った利用者や親などに残額の一括返還を求める訴訟が激増している。機構が発足した2004年度の58件に対し、12年度は百倍を超える6193件に上った。
── 東京新聞 2016.01.03
平成25年度末の段階で、奨学金を返済する義務のある人が約342.4万人。うち18.7万人が3ヶ月以上滞納しているそうなので約5.5%が滞納者ということでして、これはかなりの率と言えるでしょうね。
別に法外な利息がついて債務者を追い詰めるという話でもありません。
利息はせいぜい1%前後ですし、延滞利息が付いても+5%(⇒資料ページ)。事情があれば延滞、減額も認められますし。
そういう、かなり条件のいい形でお金を借りておきながら、借りたお金を返さないというのは言語道断です。
日本学生支援機構が滞納者に対して訴訟を起こすことを非難する理由はカケラも見当たりません。
とはいえ、この奨学金という制度のあり方に問題があることは確か。
それは制度自体の問題ではなく、「大学に行く」ことの価値が変わってきたこと、そこに当事者が無頓着過ぎることによって生じる問題です。
本人に「大学進学は自己投資」という意識がなさすぎる
一番の問題は「大学に行く」ということが、自分の人生にとってどういう意味と価値を持つのかという問題意識が、本人(とその保護者)に希薄なことでしょう。
20年前なら「大学に行く」ことは「それなりの企業に正社員として就職する」パスポートのような意味がありました。その前提があれば、奨学金をもらってでも大学に行く価値があると、ほぼ無条件に言えたわけです。
しかし、今となってはそれは幻想でしかありません。
奨学金をもらうということは、4年間のモラトリアムを自腹で買うということです。言ってみれば超高額な自己投資。
そのモラトリアム期間に、投資した金額に見合う運用益=自己成長を手に入れなければ、そりゃ借金で苦しむことになろうというもの。
学校は「大学進学を勧める」ことの責任を果たしていない
奨学金は利率の低い教育ローンです。しかも債務者が「大学に行った本人」の。
しかし、高額な借金の契約を結ぶにしては、そのリスク説明などがあまりにずさんです。
学生支援機構は2013年のNHKの番組で、奨学金の窓口は学校であるべきで、そのリスクの説明は学校でなされるべきと語っています。一方、当事者たる学校関係者は同じインタビューで、そのような説明はできていないと語っています。
進学校は「とにかく4年制大学に行け」と生徒にはっぱをかけ、「我が校の大学進学実績」をアピールしたがります。
それならば、肝心の「大学に行くことの投資対効果」について現状を子どもと保護者に説明すべきですし、そこに「借金を背負わせて進学させる」ことに対する説明責任は一定レベル果たすべきです。
その上で「それでも大学に行く価値はあるし、応援するよ」というべきなのです。
本人も、親も学校も「大学に行く価値」の見直しを!
この奨学金問題は、根本的には「当事者が揃いも揃って、大学進学を安易に考えすぎる」ことにあります。
学校は、大学進学の価値が下がっていること、大学に行けば納得のいく就職につながるわけではないことを、しっかりと生徒達に伝えなければなりません。
保護者も「奨学金を受ける=子どもに借金を背負わせる」ことだと理解した上で、子どもと人生設計を十分に話し合わなければなりません。
もし、子どもへの投資として「大学に行かせてやろう」と考えるなら、子どもが小学校低学年のうちにちゃんと学資保険だとか不動産投資だとか、何らか「その時への備え」を考えておくのが筋というもの。それができていなかったのであれば、せめて子どもにそのことをちゃんと話しましょうよ。
そして大学に進む本人には、大学に行くことが「正社員のゲートの前に立つ」程度の意味しかないことを理解させておかなければ。
正社員として迎えてもらうにせよ、違う形で活躍するにせよ、何らかリターンを得たいなら大学時代の4年間に「リターンが得られるような、それなりの過ごし方」を考えさせなければなりませんね。
それを伝えるのは、その子と関わるすべての大人の責任です。
いずれにしても、大学に行くのが当然とはいえない時代というより、大学に行って何をするかが問われる時代になったという認識を、教育者も保護者もしっかりと持って、子どもと人生のことを語り合っておきたいものです。